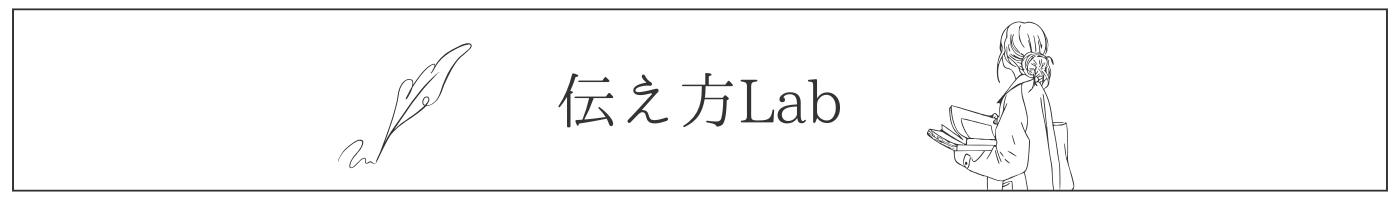「了解しました」は失礼?正しい敬語とビジネスでの使い分け方を徹底解説
ビジネスメールやチャットでつい使ってしまう「了解しました」。
一見、丁寧に聞こえますが、目上の相手に使うと“失礼”とされる場合があるのをご存じでしょうか。
「承知しました」との違いが分からず、
「どっちを使えばいいの?」「メールで間違えたかも…」と不安になる人は多いものです。
本記事では、「了解しました」と「承知しました」「かしこまりました」の正しい使い分け方を、
わかりやすい例文つきで解説します。
敬語に自信がない方でも、この記事を読めば
今日から安心して使える“感じの良い返答”ができるようになります。
なぜ「了解しました」は失礼だと言われるのか?

「了解」は目上から目下への言葉として使われてきた歴史的背景
「了解」という言葉はもともと、軍隊や官公庁などの上下関係が明確な場で使われてきた言葉です。
命令や指示に対して「了解!」と返す文化があったため、目上から目下に向けての言葉として定着しました。
その名残から、ビジネスシーンでは「了解しました」と言うと、
「上司の立場で返している」「目上の相手に対して偉そうに聞こえる」と感じる人が今でも多いのです。
つまり、「了解しました」は敬意を欠いた表現ではなくても、上下関係の印象が残っているため、
相手によっては「失礼」と受け取られるリスクがあるというわけです。
ビジネスシーンでは“敬意が足りない”と誤解されやすい
現代のビジネスでは、メールやチャットなど、文字だけのやり取りが中心です。
そのため、声のトーンや表情が伝わらず、言葉の印象だけで“冷たい”“軽い”と判断されてしまうことがあります。
たとえば、
「了解しました」
という一文だけ送ると、相手によっては「上から」「ぶっきらぼう」と感じることも。
実際、ビジネスマナーの講師や採用担当者の間でも、
「上司や取引先には『承知しました』のほうが丁寧」と教えられるケースが一般的です。
つまり、「了解しました」は決して間違いではないものの、
“敬意を伝える”という点でやや弱い表現といえるのです。
正しい敬語に言い換えるだけで印象が良くなる
「了解しました」は便利で使いやすい言葉ですが、
相手や場面に合わせて言い換えるだけで、メールの印象は大きく変わります。
たとえば、
- 上司や取引先 → 「承知しました」「承知いたしました」
- サービス業・お客様対応 → 「かしこまりました」
- 同僚・部下・社内チャット → 「了解です」「わかりました!」
このように使い分けることで、“正しい敬語”を使う人=信頼できる人という印象を与えられます。
言葉は小さな違いでも、相手への配慮が伝わる大切な要素です。
「了解しました」と「承知しました」の正しい使い分け方
「了解しました」と「承知しました」は、どちらも「内容を理解した」という意味で使われます。
しかし、敬語としての“使える場面”や“相手との関係性”によって、正しい使い方が異なります。
間違えると、意図せず「失礼」と思われてしまうこともあるため、しっかりと区別して覚えておきましょう。
「了解しました」=同等・目下への返答
「了解しました」は、基本的に同等または目下の立場の人に対して使う表現です。
語源的に「了解」は“理解して受け入れる”という意味を持ち、
上司や取引先などの目上に使うと、「上から指示を受けたような印象」を与えることがあります。
そのため、ビジネスシーンでは以下のような使い方が自然です。
✅ 使用例
- 同僚への返信:「了解しました!明日の会議で共有しますね。」
- 部下への返答:「資料の件、了解しました。進めてください。」
- 社内チャットなどで軽く確認する際:「了解です!」
⚠️ 注意点
外部の人(取引先や上司)に使うと、「軽い印象」や「無礼」と受け取られることがあるため、避けるのが無難です。
「承知しました」=目上・フォーマルな返答
「承知しました」は、敬語の中でもフォーマルで丁寧な表現です。
相手の指示・依頼・要望などを「確かに受け取りました」という意味で伝えるときに使います。
「了解しました」と同じ“理解・了承”のニュアンスを持ちますが、
より敬意と丁寧さを感じさせるため、上司やクライアントへの返答には最適です。
✅ 使用例
- 上司への報告:「承知しました。明日までに資料をまとめます。」
- 取引先へのメール:「ご依頼の件、承知いたしました。」
- クライアント対応:「日程の変更、承知いたしました。」
💡 補足
「承知いたしました」は「承知しました」よりも一段丁寧な謙譲表現です。
書面や社外メールでは「承知いたしました」を使うのがより好印象です。
どちらを使うかは“相手との関係性”で決まる
最も大切なのは、「どちらが正しいか」ではなく、相手に対してどう使い分けるかという視点です。
状況別に見ると、次のように整理できます。
| 相手・場面 | 適切な言い方 | 備考 |
|---|---|---|
| 上司・取引先 | 承知しました/承知いたしました | フォーマル・敬意を示す場合 |
| 同僚・チーム内 | 了解しました/了解です | カジュアルで自然な印象 |
| 部下・後輩 | 了解しました | 指示・承認を伝える際に適切 |
| お客様対応(接客) | かしこまりました | 最上級の敬語表現 |
このように、相手の立場や関係性によって言葉を切り替えることが、
ビジネス敬語をスマートに使いこなすポイントです。
【例文付き】使う相手別の正しい言い方一覧

「了解しました」と「承知しました」は、どちらも間違いではありません。
ただし、相手やシーンに合わせて使い分けることで、ビジネスの印象は大きく変わります。
ここでは、「上司」「同僚」「クライアント」「社内チャット」など、
よくある場面ごとの 正しい言い方例とNG例 を紹介します。
| シーン | NG例 | OK例 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 上司への返答 | 了解しました | 承知しました/かしこまりました | 「了解しました」はフラットな印象で、目上には不向き。上司や取引先などには「承知しました」や、より丁寧な「かしこまりました」を使うと好印象です。 |
| 同僚・部下への返答 | 承知しました | 了解しました(または了解です) | 同僚・部下には「了解しました」や「了解です」で十分。堅すぎず、柔らかく自然なやり取りができます。 |
| クライアント宛メール | 了解しました | 承知いたしました/かしこまりました | 社外メールでは、「承知いたしました」や「かしこまりました」が最も無難。敬意と誠実さが伝わる表現です。 |
| カジュアルな社内チャット | 承知しました | 了解です/わかりました! | チャットツールなどの軽いやり取りでは、「了解です」「わかりました!」が自然。親しみやすくテンポの良い印象を与えます。 |
💡使い分けのコツ
- 目上には「承知しました」、社外なら「承知いたしました」
- 同僚・部下には「了解しました」で十分
- チャットではやわらかく「了解です」や「わかりました!」
シーン別に使い分けるだけで、
「この人、言葉づかいがきちんとしてる」と信頼感を持たれるようになります。
使用シーン別 例文まとめ
上司宛(メール)
ご指示の件、承知しました。本日中に対応いたします。
クライアント宛(メール)
ご依頼内容、承知いたしました。詳細は改めてご連絡いたします。
同僚宛(チャット)
了解しました! データ更新後に共有しますね。
部下宛(口頭)
了解です。 そのまま進めてください。
このように、相手や媒体によって使い分けることで、
自然で丁寧な印象を与えることができます。
「承知しました」と「かしこまりました」の違い
「承知しました」と「かしこまりました」は、どちらも“理解・了承”を意味する丁寧な敬語表現です。
ただし、使う相手・場面・業種によって印象や適切さが変わります。
どちらも「正しい」言葉ですが、TPOを意識して使い分けることが、ビジネスメールや会話での信頼感につながります。
「承知しました」は社内外問わず使える万能表現
「承知しました」は、ビジネス敬語の中でも最も汎用性の高い表現です。
上司・取引先・お客様など、どんな相手にも失礼なく使える“万能フレーズ”として定着しています。
意味としては「理解しました」「把握しました」とほぼ同じですが、
より丁寧で柔らかい印象を与えるのが特徴です。
✅ 使用例
- 「ご依頼の件、承知しました。本日中に対応いたします。」
- 「資料の修正版、承知しました。確認次第ご連絡いたします。」
「承知しました」はフォーマルながらも、過度な堅苦しさがないため、
メール・会話・報告・謝罪などあらゆるビジネスシーンで使いやすい敬語です。
「かしこまりました」は接客・サービス業などで最上級の敬語
「かしこまりました」は、「承知しました」よりもさらに丁寧で、最上級の敬語表現にあたります。
主に、ホテル・販売・コールセンターなどの接客業で使われる言葉で、
お客様に対して“深い敬意”を示す際に使われます。
✅ 使用例
- 「ご注文の件、かしこまりました。すぐに手配いたします。」
- 「少々お待ちくださいませ、かしこまりました。」
ただし、社内メールや日常のビジネス会話で多用すると、やや大げさ・形式的に感じられることもあります。
上司や取引先に使う場合も問題はありませんが、
「承知しました」よりも“距離感がある”印象になる点に注意が必要です。
過剰な敬語にならないバランス感覚が大切
ビジネスの場では、「丁寧=正解」ではありません。
大切なのは、相手との関係性や状況に合った“自然な丁寧さ”を選ぶことです。
たとえば、
- 社内連絡で「かしこまりました」は堅すぎる
- 接客や初対面で「了解しました」は軽すぎる
というように、同じ「了承」の表現でも、相手によって最適な言葉は変わります。
💡敬語マナーの基本
| 状況 | おすすめ表現 | 備考 |
|---|---|---|
| 上司・取引先への返信 | 承知しました | 無難でビジネス標準 |
| お客様対応・接客 | かしこまりました | 最上級の丁寧さを表す |
| 社内でのやり取り | 了解しました | フラットで自然 |
| フォーマルな書面 | 承知いたしました | 敬語+謙譲語の組み合わせで最も丁寧 |
言葉づかいは“丁寧さ”より“適切さ”が信頼を生む──
このバランス感覚こそが、社会人としての品の良さをつくります。
感じの良い返事に変わる便利な言い換えフレーズ
「了解しました」や「承知しました」だけでは、無機質な印象になりがちです。
少し表現を変えたり、ひとこと添えたりするだけで、相手に「感じが良い人だな」と思われる返事になります。
ここでは、ビジネスメールや会話で使える便利な言い換えフレーズを紹介します。
「承知いたしました」「確認いたしました」「拝見いたしました」など用途別例
ビジネスでは、シーンに合わせた丁寧な言い方を選ぶことが重要です。
以下のように、目的ごとに適切な言い換えを使い分けると、自然で上品な印象を与えられます。
| 用途 | 基本表現 | 言い換えフレーズ | 補足・使い方例 |
|---|---|---|---|
| 指示・依頼を受けたとき | 承知しました | 承知いたしました | より丁寧。社外メールや上司宛に最適。 |
| 内容を確認したとき | 確認しました | 確認いたしました | 書類・資料チェック後の返信に使える。 |
| 書類・資料を読んだとき | 見ました | 拝見いたしました | 目上への「見ました」は避け、「拝見〜」で丁寧に。 |
| 依頼を引き受けるとき | わかりました | 承りました | フォーマルな返信・接客メールでよく使う。 |
| 日程や提案を受けたとき | 了解しました | 検討いたします/確認いたします | すぐ返事できないときの柔らかい言い換え。 |
このように、同じ「了承・確認」でも、シーンに応じた敬語の選択が信頼につながります。
「いつもありがとうございます」など感謝を添えるだけで印象アップ
どんなに正しい敬語でも、「冷たい」「事務的」と感じられることがあります。
そんなときは、感謝のひとことを添えるだけで印象が一気に変わります。
✅ 使える感謝フレーズ例
- 「いつもご丁寧にありがとうございます。」
- 「ご連絡いただき、誠にありがとうございます。」
- 「迅速なご対応、感謝申し上げます。」
- 「ご確認くださり、ありがとうございます。」
これらを文末に加えるだけで、メール全体が柔らかくなり、誠実で温かい印象を与えられます。
💡たとえば
ご連絡の件、承知いたしました。いつもありがとうございます。
このような一文を添えるだけで、「機械的な返事」から「心のこもった返答」に変わります。
クッション言葉を加えるとより自然に
直接的な依頼や指示の前後に“クッション言葉”を入れると、よりやわらかく伝わります。
これは、ビジネスメールの印象を良くする言葉づかいの基本です。
✅ よく使われるクッション言葉
| 用途 | フレーズ例 | 使用シーン |
|---|---|---|
| 依頼の前 | 恐れ入りますが/お手数ですが | 「恐れ入りますが、こちらのご確認をお願いいたします。」 |
| 注意・お願い | 失礼ですが/恐縮ですが | 「恐縮ですが、再度ご確認いただけますと幸いです。」 |
| 返信・対応時 | ご対応ありがとうございます/ご連絡感謝いたします | 相手の手間に対して感謝を伝える |
| 柔らかいお願い | 差し支えなければ/可能であれば | 「可能であれば、明日までにご返信ください。」 |
クッション言葉を意識的に使うことで、相手に圧を与えず、誠実さを伝えることができます。
単なるマナーではなく、円滑なコミュニケーションを築くための“思いやりの言葉”です。
まとめ|敬語は“正しさ”より“思いやり”で印象が決まる
ビジネスにおける言葉づかいは、単なるルールや形式ではありません。
大切なのは、相手を思いやる気持ちをどう表現するかという姿勢です。
「敬語を完璧に使える人」よりも、「感じの良い話し方ができる人」が最終的に信頼を得ます。
相手を立てる意識が正しい言葉遣いを導く
敬語を使う目的は、「自分をへりくだること」ではなく、相手を立てることにあります。
たとえば、「承知しました」「かしこまりました」なども、
相手への敬意を込めるための“表現の道具”です。
言葉を丁寧に選ぶ姿勢は、それだけで「この人は信頼できる」と感じてもらえる要素になります。
つまり、敬語のコツは文法ではなく、相手への敬意を意識することなのです。
「了解しました」も場面によってはOK
「了解しました」は一概に“失礼”ではありません。
ビジネスメールの世界では、「相手との関係性」「やり取りの距離感」によって使い分ける柔軟さが大切です。
- 上司や取引先 → 「承知しました」「かしこまりました」
- 同僚や社内連絡 → 「了解しました」「了解です」
このように使い分けることで、堅苦しくなりすぎず、自然で気持ちの良いやり取りができます。
「言葉の正しさ」よりも、「相手がどう感じるか」を意識することが印象を左右します。
「伝え方Lab」では言葉遣いのマナーと印象改善術を発信中
本記事のように、「伝え方Lab」ではビジネス・日常会話・メールなど、
あらゆるシーンで役立つ丁寧な話し方や言葉遣いの改善術を紹介しています。
「間違っていないけれど、ちょっと堅い」
「正しいけれど、冷たく感じる」
そんな“言葉の温度差”を埋めるヒントを、今後も発信していきます。
最後に:ことのは先生よりひとこと

言葉は“心のかたち”です。
「正しい敬語を使わなきゃ」と身構えるよりも、
「相手に気持ちよく受け取ってもらうには?」と考えることが、丁寧な話し方の第一歩。
言葉ひとつで、信頼も印象も変えられます。
あなたの「伝え方」が、今日から少しやさしく、あたたかいものになりますように。